世界中でパンデミックとなっている新型コロナウイルスの感染を防ぐためには、密閉、密集、密接という3密を避け、ソーシャルディスタンス(社会的距離)をとり、手洗いをすることが有効とされています。
これらの予防法は新型コロナウイルスが飛沫や接触により感染するというメカニズムにもとづきます。いまだに効果的な治療薬やワクチンがない現状では、感染を防ぐための「知識」がとても重要になるのです。
そして現在、もうひとつのパンデミックが起ころうとしています。
それが「肥満」です。
2030年には米国人の2人に1人(48.9%)が肥満になり、4人に1人(24.2%)が重度の肥満になることが予測されています(Ward ZJ, 2019)。
これまでに数多くのダイエット方法が報告されてきましたが、いまだ効果的なものはありません。効果的な治療法がないのであれば、重要になるのが太ることを予防するための知識であり、「太るメカニズム」を知ることです。
新型コロナウイルスの感染予防として3密を避けるように、太るメカニズムを知っていれば、太る要因となるものを避けることができるのです。
前回は、ショートケーキを題材に「糖類による太るメカニズム」について考察してきました。
ケーキに含まれる単糖類のグルコースはインスリンの作用によって脂肪組織に取り込まれます。また、過剰に摂取した場合や、習慣的に摂取すると筋肉にインスリン抵抗性が生じて、より多くのグルコースが脂肪組織に取り込まれてしまい、脂肪細胞が肥大します。
もう一つの単糖類であるフルクトースを過剰に摂取すると、肝臓から脂質を多く含むリポタンパク質が血液中に放出され、脂肪組織に取り込まれることによって脂肪細胞を肥大化させます。これだけでなく、フルクトースには食欲促進ホルモンの分泌を高める作用があり、「もっと食べたい」という欲求を増大させます。この作用によって過剰な糖類を摂取してしまい太るのです。
このような糖類による太るメカニズムを知れば、多くの砂糖や異性化したフルクトースである高果糖ブドウ糖液糖を含むケーキやジュースの食べ過ぎ、飲み過ぎを防ぐことができるでしょう。
『ダイエットするなら「太るメカニズム」を理解しよう!〜糖類編〜』
そして、ケーキに含まれるのは糖類だけではありません。
「脂質」も含まれています。
脂質は三大栄養素のひとつであり、エネルギーの貯蔵や細胞膜の構成成分、脂溶性ビタミンを運ぶ担体としての役割などを担っており、身体にとっては重要な栄養素です。しかし、過剰に摂取してしまうと、太らせる栄養素になります。
脂質のエネルギー量は1gあたり9kcalであり、これは糖質やタンパク質のエネルギー量(1gあたり4kcal)の2倍以上です。それだけ脂質は太りやすい栄養素なのですが、現代の栄養学は、脂質が僕たちを太らせる「もうひとつの要因」を明らかにしつつあるのです。
今回もショートケーキを題材にして、「脂質による太るメカニズム」について考察していきましょう。
Table of contents
- ◆ 脂質の正体「トリアシルグリセロール」とは?
- ◆ 脂質はカプセルに乗って体脂肪へ運ばれる
- ◆ なぜ、脂質を「美味しい」と感じるのか?
- ◆ 脂質中毒という怖いワナ
- ◆ ダイエットの科学シリーズ
- ◆ 参考文献
◆ 脂質の正体「トリアシルグリセロール」とは?
ショートケーキは、小麦粉、バター、卵(鶏卵)、ホイップクリーム、そして大量の砂糖からつくられます(イチゴは省きます)。
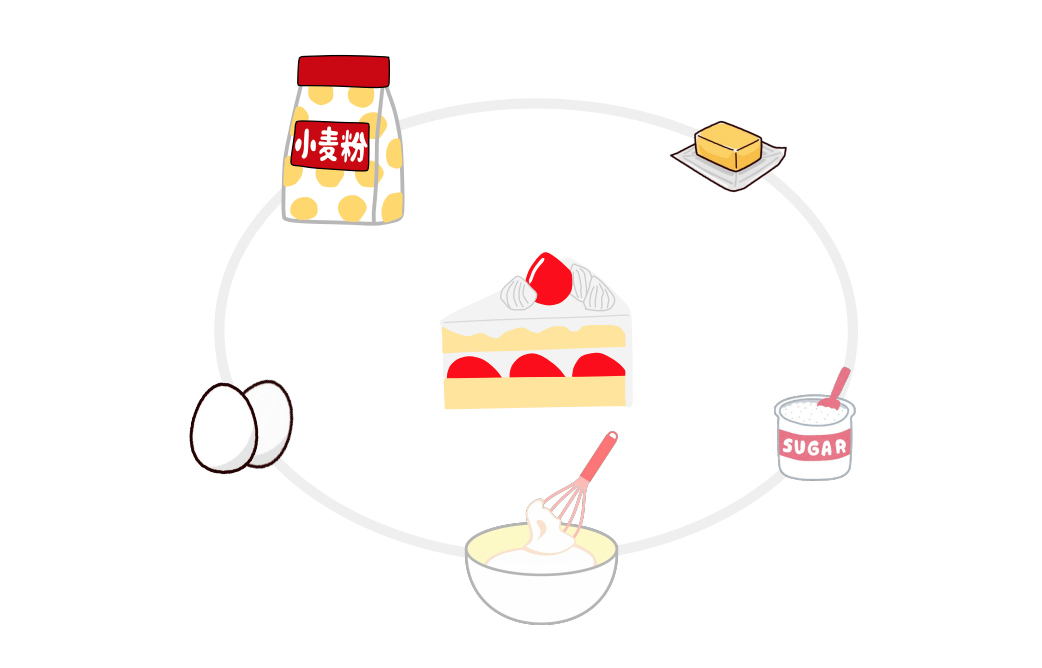
図1:ショートケーキの材料
このなかで卵やバター、ホイップクリームの成分が脂質になります。

図2:ショートケーキの脂質成分
脂質とは、栄養学の領域で使われる用語であり「水に溶けない高エネルギー物質の総称」とされています。具体的には、中性脂肪をはじめコレステロール、リン脂質や糖脂質、遊離脂肪酸などを含みます。
僕たちのおなかにある体脂肪は中性脂肪であり、脂質になります。そして、そのほとんどがトリアシルグリセロールというグリセロール(アルコールの一種)に3つの脂肪酸がくっついた(エステル結合した)ものになります。

図4:トリアシルグリセロールの構成
また、食品に含まれる脂質もほとんどがトリアシルグリセロールであり、卵やバター、ホイップクリームの成分もトリアシルグリセロールで構成されています。このように、脂質というのは多くの場合で「トリアシルグリセロール」のことを指しています。
では、ショートケーキを食べたあとの脂質の消化・吸収を見ていきましょう。
ショートケーキを食べると、卵やバター、ホイップクリームに含まれるトリアシルグリセロールはおもに小腸で消化吸収されます。
トリアシルグリセロールは、グリセロールに3つの脂肪酸がくっついたものですが、脂肪酸は炭素でできた骨格(これを炭素鎖といいます)の両端にカルボキシ基とメチル基をもつ構造をしています。

また、脂肪酸の骨格である炭素鎖の長さ(炭素の個数)によって、長鎖、中鎖、短鎖という3つの脂肪酸に分類されます。

図6:炭素鎖の長さによる脂肪酸の分類
長鎖脂肪酸は炭素鎖の炭素の数が12個以上のものをいい、卵の卵黄やバターに多く含まれるパルミチン酸やステアリン酸、オレイン酸などは長鎖脂肪酸になります。
中鎖脂肪酸は炭素の数が8個と10個、短鎖脂肪酸は4個と6個のものをいい、バターの一部の脂肪酸やホイップクリームの原料である乳脂肪が短鎖・中鎖脂肪酸になります。
そして、この長鎖脂肪酸と中鎖・短鎖脂肪酸は、小腸で異なる消化吸収が行われます。
◆ 脂質はカプセルに乗って体脂肪へ運ばれる
まずは長鎖脂肪酸の消化・吸収を見ていきましょう。
長鎖脂肪酸をもつトリアシルグリセロールは、小腸で消化酵素であるリパーゼによって2つの脂肪酸とモノアシルグリセロール(グリセリン+1つの脂肪酸)に分解されて上皮細胞に吸収されます。
吸収された長鎖脂肪酸は上皮細胞の中で活性化されてアシルCoA(活性化した脂肪酸)となり、再びモノアシルグリセロールと結合してトリアシルグリセロールになります。

図7:長鎖脂肪酸の消化・吸収
トリアシルグリセロールはそのままでは血液に溶けないため、コレステロールなどを加えて「リポタンパク質(脂質とタンパク質の複合体)」のカイロミクロン(キロミクロン)を形成して、リンパ管をとおって血液中に放出され、全身の脂肪組織に送られます。

図8:カイロミクロンの形成と放出
リポタンパク質は血液中で脂質を小さな粒状にして輸送するカプセルのようなものであり、脂質を親水性の高いリン脂質やタンパク質の殻にいれて形つくられています。
リポタンパク質は含まれるトリアシルグリセロールの量に応じてカイロミクロン、VLDL、LDL、HDLに分けられます。カイロミクロンやVLDLは脂質をもっとも含むリポタンパク質であり、トリアシルグリセロールの含有率は55〜86%になります。

図9:リポタンパク質の分類
血液中に放出されたカイロミクロンは、豊富に含んだトリアシルグリセロールから脂肪酸を皮下脂肪や内臓脂肪に放出します。脂肪組織は放出された脂肪酸を取り込み、トリアシルグリセロールを合成することによって脂肪細胞が肥大させます。これにより、太ります。
長鎖脂肪酸に対して、ホイップクリームやバターの一部の成分である中鎖・短鎖脂肪酸をもつトリアシルグリセロールの消化吸収は少し異なります。
中鎖・短鎖脂肪酸をもつトリアシルグリセロールも同じように小腸でリパーゼによって脂肪酸とグリセロールに分解されます。分解された短鎖・中鎖脂肪酸は、長鎖脂肪酸とは異なり、トリアシルグリセロールに再合成されることはありません。脂肪酸のまま門脈をとおって肝臓に送られます。

図10:中鎖・短鎖脂肪酸の消化・吸収
肝臓に送られた中鎖・短鎖脂肪酸はミトコンドリアで酸化され、エネルギー源として利用されます。残った脂肪酸はトリアシルグリセロールに再合成され、コレステロールと一緒にリポタンパク質であるVLDL(超低比重リポタンパク質)になって血液中に放出されます。
VLDLはトリアシルグリセロールを55%含む脂質リッチなリポタンパク質であり、カイロミクロンと同じように、全身の皮下脂肪、内臓脂肪に脂肪酸を供給します。脂肪酸を受け取った脂肪組織はトリアシルグリセロールを合成して脂肪細胞を肥大させます。

図11:VLDLの形成と放出
中鎖脂肪酸はとくにミトコンドリアで酸化されやすく、長鎖脂肪酸と比べて「体脂肪になりにくい脂肪酸」とされています(Aoyama T, 2007)。
ショートケーキを食べると、卵やバター、ホイップクリームに含まれる長鎖脂肪酸や中鎖・短鎖脂肪酸をもつトリアシルグリセロールは、代謝の経路は異なりますが、最終的にはそれぞれカイロミクロンやVLDLといったカプセルに乗って全身の皮下脂肪、内臓脂肪に送られ、脂肪細胞を肥大させるのです。
また、カイロミクロンやVLDLが脂肪組織に脂肪酸を運び終えると、コレステロールを多く含むLDL(悪玉コレステロール)になります。血液中にLDLが多くなると、健康診断で悪玉コレステロールが高いと言われ、脂質異常症や動脈硬化の要因になります。脂質を過剰に摂取すると悪玉コレステロールが高くなるのは、このためです。
このように脂質は、そのエネルギー量の多さから過剰に摂取すると直接的に脂肪細胞を肥大させることから、太りやすい栄養素とされているのです。
もちろん、脂質を食べ過ぎなければ問題ないのですが、僕たちは脂質の多い食品を「美味しい」と感じ、ついつい多く食べてしまいます。
これは、なぜなのでしょうか?
◆ なぜ、脂質を「美味しい」と感じるのか?
テレビでハンバーグから肉汁があふれだすシーンを見ると、思わず「ゴクリ」と唾液を飲み込みますよね。赤身の肉よりも霜降り肉のほうが人気がありますし、マグロも赤身よりも脂質の多い中トロや大トロが好まれます。
甘味、酸味、塩味、苦味、うま味といった5つの味覚は、その食物が身体にとって有益なのか、それとも有害なのかを弁別するセンサーの役割を担っています。
たとえば、脳の重要なエネルギーであるグルコースは「甘い」と感じます。筋肉をつくるタンパク質は「うま味」として摂取されます。細胞の機能を維持するための適量なナトリウムは「塩味」として要求されます。
また、身体にとって有害となる多量なナトリウムは「しょっぱい」と感じ、腐った食物は「酸味」として、毒物は「苦味」として感じ、避けるように生得的にプログラミングされています。
では、脂質はどのような味がするのかというと「無味」です。
脂質は無味無臭であり、5つのどの味覚にも感知されないのです。
しかし、脂質のエネルギー量は糖質やタンパク質よりも2倍も多く、脂質はエネルギーを貯蔵するには効率的な栄養素になります。
そのため、脂質を「美味しい」と感じることは、ヒトの生存にとって有益であり、その味覚の存在の検証が現代の栄養学のトピックスになっていたのです。
そして近年、脂質を美味しく感じる「第6の味覚」の存在が少しづつ明らかになってきました。
ハンバーグなどの脂質を含む食品を食べると、含まれている長鎖脂肪酸のトリアシルグリセロールは舌リパーゼという酵素の働きによって、その一部の脂肪酸が分離されます。遊離した脂肪酸は舌にある味蕾細胞の上にあるCD36という脂肪酸の輸送体によって細胞の中に運ばれます。
脂肪酸が細胞の中に入ると神経細胞が刺激され、脳内にβエンドルフィンが分泌されます。このβエンドルフィンは「快感」を感じさせる伝達物質であり、この快感が脂質の美味しさの正体であることが示唆されています(Philippe B, 2016)。

図12:脂質を美味しく感じるメカニズム
このような脂質を美味しく感じる第6に味覚によって、僕たちは脂質を含む食事を「美味しい」と感じているのです。
そして、この第6の味覚をハックしているのが現代の食品業界です。
ケーキやポテトチップスなどのお菓子、ハンバーガーなどのファーストフードは、加工した脂質を使用することによって第6の味覚をハックし、「美味しい」という快感を与え、「もっと食べたい」と思わせることによって僕たちを太らせるのです。
その結果として最近、新たに提唱されているのが「脂質中毒」です。
◆ 脂質中毒という怖いワナ
お腹が空くと、「食べたい」という食欲が生じます。これは生存のために食べる行動であり「恒常性維持に関わる摂食」といいます。これに対して、「美味しい」という感覚を得るために食べる行動を「嗜好性にもとづく摂食」といいます。
食べるという行動には、ふたつの側面があり、それぞれにメカニズムが異なります。そして脂質の摂取は、後者の「嗜好性にもとづく摂食」を促進します。
嗜好性は脳にある「報酬系」が大きく影響しており、食べるという行動を行った結果、自分か予想していたよりも「美味しかった」という快感を感じたときに脳の報酬系が作用します。これにより、快感のもととなった行動がより「強化」されるのです。
脂質が豊富なケーキやポテトチップスなどを食べると、第6の味覚が脂質を感知し、脳内でβエンドルフィンを分泌させ「美味しい」という快感を与えます。
すると、この情報が中脳の腹側被蓋野に送られ、ドーパミン作動性ニューロンが興奮し、側坐核という部分にドーパミンを放出します。これにより「美味しい」という快感(報酬)を得た行動(脂質が豊富な食品を食べる)が強化されるのです。
しかし、習慣的に報酬系が作用すると、誤作動が生じます。
それが「中毒化」です。報酬系のやっかいなところは、依存性になるということです。
アルコールやタバコ(ニコチン)、ドラッグでも習慣的に摂取することによって耐性ができ、「もっと摂取したい」という依存性を生じさせます。
もちろん脂質にはニコチンのような習慣性物質は含まれていませんが、脂質が多く含まれている嗜好性の高い食品を習慣的に摂取すると、脂質の味覚に耐性が生じ「もっと食べたい」という依存性を生じさせる「脂質中毒(Fat Addiction)」が近年、示唆されるようになったのです。
脂質中毒について最新のレビューを報告したのがインド・国立薬物依存治療センターのSiddharthらです。
Siddharthらは、高脂質な食品を習慣的に摂取していたラットに電気ショックを加えても、その摂取行動をやめることなく食事をたいらげてしまうという、脂質中毒を示唆する動物研究を例に挙げて、脂質を好むヒトの注意バイアスや特異的な食事パターンの存在を示唆した研究報告をレビューしています。
脂質に依存的なヒトは、食品を選ぶとき、無意識に脂質の多い食品へ注意が向いてしまうという「注意バイアス」が認められています。その食事パターンは肉、バター、甘味のあるクリームデザートやクロワッサンなどのような高脂質の食品の摂取量が多くなり、繊維、果物、野菜、ヨーグルトなどの低脂質な食品の摂取量が少なくなる傾向が報告されています。
このような研究結果から、Siddharthらは脂質の習慣的な摂取は、脂質の嗜好性を高め、それにともなう注意バイアスが肥満を促進させる要因になっていると警鐘を鳴らしています(Siddharth S, 2019)。
脂質は三大栄養素のひとつとして挙げられるように、身体にとって重要な栄養素です。しかし、総摂取カロリーが総消費カロリーを上回っている「オーバーカロリー」のときには、脂質は太る栄養素に変わります(Hellerstein MK, 1999)。
ショートケーキなどの脂質リッチな食品を摂取すると、含まれている脂質はリポタンパク質というカプセルに乗って、直接的に皮下脂肪や内臓脂肪に届けられ、脂肪細胞を肥大させます。
さらに、脂質の口当たりの良さや美味しさは第6の味覚から脳内に「快感」をもたらします。これが報酬系を作動させ、習慣的に摂取することによって嗜好性が高まり、「脂質中毒」とされる依存性を生じさせることが示唆されています。すると、無意識に脂質の多い食品を選択してしまうという注意バイアスがはたらき、さらに脂質を摂取することで太ってしまうのです。
脂質の多いケーキやポテトチップス、ファーストフードを習慣的に食べているのであれば、このような「脂質による太るメカニズム」を思い出してみましょう。そうすれば脂質の美味しさが招く中毒性のワナから逃れられるはずです。
これまで2回にわたり、糖類と脂質による「太るメカニズム」について考察してきました。それぞれに太るメカニズムがありますが、現代の食品業界はこれらのメカニズムを上手にハックして僕たちを太らせようとします。
その代表が「ファーストフード」です。
2019年、ファーストフードの摂取量の増加と体重の増加に関連があることが報告されました(Hall KD, 2019)。ハンバーガーやポテト(過剰な脂質)に甘い炭酸飲料(過剰な糖類)を組み合わせた「セットメニュー」は大人気ですが、そこには僕たちを太らせる「巧妙な仕掛け」があるのです。
次回は、ファーストフードによる太るメカニズムを考察していきましょう。
◇ ダイエットの最新エビデンスをまとめた新刊です!
◇ こちらもセットで是非!
◆ ダイエットの科学シリーズ
シリーズ1:「朝食を食べないと太る」というのは都市伝説?〜最新エビデンスを知っておこう
シリーズ2:ダイエットが続かないのは「寝不足」が原因?【最新エビデンス】
シリーズ3:テレビをつけたまま寝ると太る最新エビデンス
シリーズ4:コーヒーにはダイエット効果がある?【最新エビデンス】
シリーズ5:ダイエットするなら「太るメカニズム」を理解しよう!〜糖類編〜
シリーズ6:ダイエットするなら「太るメカニズム」を理解しよう!〜脂質編〜
シリーズ7:筋トレをして筋肉を増やせばダイエットできる説を検証しよう!
シリーズ8:ソイ・プロテインなどの大豆食品によるダイエット効果の最新エビデンス
シリーズ9:太ると頭が悪くなる?最新エビデンスを知っておこう!
シリーズ10:ダイエットをすると頭が良くなる最新エビデンス【科学的に正しい自己啓発法】
シリーズ11:ダイエットすると筋肉量や筋力が減ってしまう科学的根拠を知っておこう!
シリーズ12:筋肉を減らさない科学的に正しいダイエット方法を知っておこう!【食事編】
シリーズ13:筋肉を減らさずにダイエットするならタンパク質の摂取量を増やそう!
シリーズ14:ダイエットで食欲を抑えたいならタンパク質を摂取しよう!
シリーズ15:タンパク質が食欲を減らすメカニズムを知っておこう!
シリーズ16:寝不足がダイエットの邪魔をする!〜睡眠不足が食欲を高める最新エビデンス
シリーズ17:ダイエットは超加工食品を避けることからはじめよう!
シリーズ18:ダイエットするなら「太る炭水化物」と「やせる炭水化物」を見極めよう!
シリーズ19:ダイエットするなら「白米よりも玄米」を食べよう!
シリーズ20:ダイエットするなら「やせる野菜と果物」を食べよう!
シリーズ21:ダイエットするなら「健康に良い、やせる脂質」を食べよう!
シリーズ22:ダイエットするなら「おやつにナッツ」を食べよう!
シリーズ23:ダイエットするなら「ジュース(砂糖入り飲料)の中毒性」を断ち切ろう!
シリーズ24:ダイエットするなら「やせる飲みもの」を飲もう!
シリーズ25:タンパク質は食べるだけでエネルギーを消費できる!〜食事誘発性熱産生を知っておこう
シリーズ26:ダイエットするなら「赤い肉」よりも「白い肉」を食べよう!
シリーズ27:ダイエット中の食べすぎを防ぎたいなら、食事の前に「冷たい水」を飲もう!
シリーズ28:タンパク質はダイエットによる骨の減少を抑えてくれる!
シリーズ29:乳製品がダイエット効果を高める最新エビデンスを知っておこう!
シリーズ30:タンパク質がダイエット効果を高める最新エビデンスを知っておこう!
シリーズ31:週末に寝だめをしても睡眠不足による食欲の増加は防げない!
シリーズ32:ダイエットするなら運動よりも食事制限から始めるべき科学的根拠
シリーズ33:ダイエットを成功させたいなら「リバウンドのメカニズム」を知ってこう!
シリーズ34:ダイエットでリバウンドを防ぐなら「運動」をするべき科学的根拠
シリーズ35:ぽっこりお腹を減らしたいならダイエットで「運動」をするべき科学的根拠
◆ 参考文献
Ward ZJ, et al. Projected U.S. State-Level Prevalence of Adult Obesity and Severe Obesity. N Engl J Med . 2019 Dec 19;381(25):2440-2450.
Aoyama T, et al. Research on the Nutritional Characteristics of Medium-Chain Fatty Acids. J Med Invest . 2007 Aug;54(3-4):385-8.
Nesse RM, et al. Psychoactive Drug Use in Evolutionary Perspective. Science . 1997 Oct 3;278(5335):63-6.
Philippe B, et al. Taste of Fat: A Sixth Taste Modality? Physiol Rev . 2016 Jan;96(1):151-76.
Siddharth S, et al. Fat Addiction: Psychological and Physiological Trajectory. Nutrients . 2019 Nov 15;11(11):2785.
Hellerstein MK, et al. De novo lipogenesis in humans: metabolic and regulatory aspects. Eur J Clin Nutr. 1999 Apr;53 Suppl 1:S53-65.
Hall KD, et al. Ultra-Processed Diets Cause Excess Calorie Intake and Weight Gain: An Inpatient Randomized Controlled Trial of Ad Libitum Food Intake. Cell Metab . 2019 Jul 2;30(1):67-77.e3.


